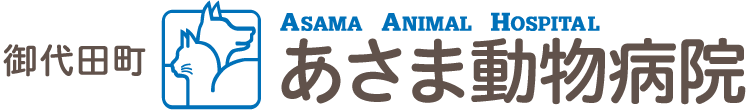犬と猫が咳をする理由とは?|症状別に考えられる病気と対処法を紹介
愛犬や愛猫が突然「ケホケホ」と咳をし始めると、びっくりしてしまいますよね。
実は、咳は単なる風邪だけでなく、気管支炎や肺炎、場合によっては心臓病といった深刻な病気のサインであることもあるんです。
さらに、咳の仕方や起こるタイミングによって原因が違うこともあります。例えば、夜に咳が多い場合や、散歩の後だけに咳き込む場合など、それぞれ注意すべきポイントがあるんです。だからこそ、「いつもの咳かな」と放置せず、早めに気づいて対処することが大切です。
今回は、犬や猫が咳をする原因や、そこから考えられる病気について詳しく解説します。
■目次
1.犬や猫の咳、どんな種類がある?
2.呼吸器の病気が原因の咳
3.心臓の病気が原因の咳
4.その他考えられる咳の原因
5.咳が出たときの対処法
6.診断方法
7.治療方法
8.予防接種の重要性
9.まとめ
犬や猫の咳、どんな種類がある?
咳にはいくつかの種類があり、その音や状況によって考えられる原因が異なります。
ここでは、代表的な咳のタイプをご紹介します。
<乾いた咳>
「カッカッ」と短く鋭い音が出る咳で、まるで何かが喉に詰まったように聞こえることがあります。
原因として多いのは、気管虚脱や感染症(例えば犬のケンネルコフ)です。
特に、愛犬が興奮しているときや、散歩中にリードが首に当たったときに起こりやすいのが特徴です。
<湿った咳>
「ゴホゴホ」と低く、胸の奥から痰が絡むような音がする咳です。この場合、肺炎や気管支炎など、呼吸器内で炎症や感染が進んでいる可能性があります。
特に、湿気の多い季節や朝方に悪化することがあります。
<発作的な咳>
突然始まって、連続して「ケンケン」と咳き込むのがこのタイプです。主な原因としては、気管虚脱や異物の誤飲が考えられます。
夜間や運動後など、特定のタイミングで起こりやすいのが特徴です。
<咳の頻度や時間帯の違い>
咳が出る時間帯や頻度によっても、原因を考える手がかりになります。
・夜間だけ咳をする場合:心臓病や肺水腫の可能性があります。
・運動後に咳をする場合:気管支炎や気管虚脱が考えられます。
・継続的に咳をする場合:感染症や慢性的な炎症が原因になっているかもしれません。
これらの情報を参考にすると、愛犬や愛猫の咳の様子を観察するポイントが少し見えてくるかもしれません。ただし、あくまでも目安ですので、正確な診断には獣医師の診察が欠かせません。
咳が気になったときは、「ちょっと相談してみようかな」という気持ちで、かかりつけの動物病院に足を運んでみてくださいね。
呼吸器の病気が原因の咳
犬や猫の咳の背景には、呼吸器の病気が隠れていることもあるので、注意が必要です。
<気管支炎>
気管支炎では、「ゴホゴホ」と湿った咳が長く続くことが多いのが特徴です。この病気が進むと、呼吸が苦しそうになることもあります。
原因としては、細菌やウイルスの感染、アレルギーが考えられます。
寒暖差が激しい季節に発症しやすいので、特に冬場は注意して様子を見てあげてください。
<気管虚脱>
気管虚脱の場合、「カッカッ」と乾いた咳が発作的に起こることがあります。特に、興奮したときに悪化しやすいのが特徴です。
この病気は気管の構造が弱くなり、空気の通り道が狭くなることで起こります。小型犬(チワワ、トイプードル、ポメラニアンなど)でよく見られる疾患です。
夏場の運動後や寒い時期に症状が悪化しやすいので、季節ごとの注意が大切です。
<肺炎>
肺炎では、「ゴホゴホ」という湿った咳に加え、発熱や元気がなくなるといった症状が見られることがあります。呼吸が荒くなることもあるので、このような状態が続く場合は早めに診察を受けてください。
肺炎の原因は、細菌や真菌の感染、誤嚥などです。
冬場や梅雨時期などに発症しやすい病気です。
<アレルギー性の咳>
アレルギー性の咳は、「カッカッ」と乾いた咳が特徴です。特に季節の変わり目に多く見られ、花粉やダニといったアレルゲンが影響しています。
春や秋に症状が出やすいので、この時期はアレルギーに配慮した環境作りを心がけましょう。
心臓の病気が原因の咳
心臓の病気、特に僧帽弁閉鎖不全症が原因で咳が出ることがあります。この病気では、心臓が血液をうまく送り出せなくなり、徐々に血液が心臓内に溜まります。
その結果、心臓が肥大して気管を圧迫し、咳を引き起こすことがあるのです。
<特徴的な症状>
心臓の病気による咳には、いくつか特徴的な症状があります。
・夜間の咳:特に横になっているときに咳が出やすくなるのが特徴です。寝ている間に「ゴホゴホ」と苦しそうにする場合は要注意です。
・息切れや呼吸困難:散歩の後や興奮時に呼吸が荒くなることがあります。
・体重減少や元気消失:心臓病が進行してくると、これらの症状が見られることがあります。
心臓病による咳は、高齢の犬や猫に多く見られる症状です。特に小型犬では、発症率が高いことが知られています。
例えば、キャバリアやポメラニアンといった犬種は、心臓病にかかりやすい傾向があります。こうした犬種を飼っている場合は、日頃から心臓の健康に注意を払うことが大切です。
その他考えられる咳の原因
咳は、呼吸器や心臓の病気だけが原因とは限りません。他にもさまざまな要因が隠れていることがあります。ここでは、考えられる代表的な原因についてお話しします。
<異物の誤飲>
異物が気管や喉に引っかかると、突然「ケホケホ」と激しく咳き込むことがあります。この場合、咳は突然始まり、激しいのが特徴です。
例:小さなおもちゃ、糸、ひも、骨などが原因となることが多いです。
<腫瘍>
腫瘍が原因で咳が出る場合、咳が長引いたり、血が混じったりすることがあります。特に高齢の犬や猫では、腫瘍が咳の原因になっている可能性も否定できません。
例:ゴールデンレトリバーなど、腫瘍が発生しやすいとされる犬種では注意が必要です。
<感染症>
感染症による咳は、「ゴホゴホ」と湿った音がすることが多く、発熱や食欲不振といった症状を伴う場合があります。
例:犬のケンネルコフや、猫のヘルペスウイルス・カリシウイルス・クラミジアが原因となる猫風邪などがあります。これらは免疫力が低下しているときや、感染リスクの高い環境で発症しやすい病気です。
<環境要因>
タバコの煙やハウスダスト、カビなどは、犬や猫の呼吸器に刺激を与え、慢性的な咳を引き起こすことがあります。
特に室内で過ごす時間が長い場合、こうした環境要因が症状を悪化させることがあるため、日常的に生活環境を見直すことが大切です。
・部屋の掃除や換気をこまめに行う
・加湿器を使って適度な湿度を保つ
・タバコの煙を避ける
咳が出たときの対処法
咳の症状が見られた場合、まずは落ち着いて、状況をよく観察してみてください。ここでは、危険信号や自宅でのケア方法についてお話しします。
<すぐに病院に行くべき危険信号>
次のような症状が見られる場合は、すぐに動物病院に相談してください。
・持続的な咳:短期間で症状が改善せず、咳が続いている場合。
・呼吸困難:口を開けて呼吸をしている、または鼻を広げて必死に呼吸しているような状態。
・血の混じった咳:呼吸器系や内臓の異常が疑われます。
・その他の異常:咳と同時に食欲不振や体重減少が見られる場合。
<自宅でできるケア方法>
軽い咳であれば、以下のようなケアを試してみてください。
・安静にさせる
咳が続いているときは、愛犬や愛猫を無理に動かさず、静かで安心できる環境で休ませてあげましょう。
・環境を整える
窓を少し開けて換気をし、新鮮な空気を取り入れましょう。また、乾燥が原因で咳が悪化することもあるため、加湿器や濡れタオルを使って部屋の湿度を40〜60%程度に保つよう心がけてください。
診断方法
病院では、咳の原因を特定するためにさまざまな検査が行われます。
・胸部レントゲン:肺や心臓の状態を確認します。
・血液検査:感染症や内臓の異常を調べるために行われます。
・エコー検査:心臓病の有無を診断するために使用されます。
治療方法
咳の原因によって治療法は異なります。動物病院では、以下のような治療が行われることがあります。
・投薬治療:抗生物質や咳止め、気管支拡張剤などが処方されることがあります。
・酸素療法:呼吸が苦しい場合に酸素を吸入させる治療法です。
・手術:異物除去や腫瘍の切除など、原因によって外科的な対応が必要な場合もあります。
予防接種の重要性
感染症が原因で咳を引き起こす病気の多くは、予防接種を受けることで事前に防ぐことができます。特に、犬のケンネルコフや猫風邪といった病気は、ワクチンによる予防が可能です。
定期的にかかりつけの動物病院で接種スケジュールを確認し、必要なワクチンを忘れずに受けさせましょう。
また、予防接種は愛犬や愛猫だけでなく、周りの犬や猫への感染を防ぐことにもつながります。特に多くの動物が集まる場所(ドッグランやペットホテルなど)を利用する場合には、ワクチン接種がより重要となります。
まとめ
犬や猫の咳は、単なる風邪から、心臓病や腫瘍などの重大な病気のサインである場合もあります。咳の性質や発生する時間帯、頻度に注意を払い、早期に異常を発見することがとても大切です。
自宅でのケアも大事ですが、咳が続く場合や危険信号が見られる場合には、迷わず動物病院に相談してください。
また、愛犬や愛猫が健やかに暮らせるよう、定期的な健康診断や予防接種をしっかり行い、安心して過ごせる環境を整えることを心がけましょう。
長野県御代田町、小諸市、佐久市、軽井沢町の動物病院なら「あさま動物病院」
診察案内はこちら